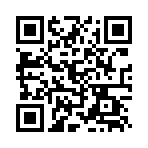2017年03月14日
勧請縄
その時代、ムラの外は異界であり、悪霊、災害や疫病は異界からムラへ侵入してくると考えられていました。疫神は、いつも村人が行き来する道から侵入してくると考えた人たちは、村の出入り口に呪物を置いて「悪霊防除」を祈願したのです。塞の神はこうした目的で、ムラの出入り口となる道路に祀られ、呪い物で道を区切りました。こうした風習が今も滋賀県の湖南、湖東地方には「勧請吊り」行事として伝承されているのです。
亀川の信号機を西老蘇に曲がるとすぐに津島さんの小さな祠があります。その脇にあるポールに、ありました、ありました、勧請縄が架かっています。「いっつも車で通ってるけど、全然気が付いてへんわ!」。その足元の植え込みの下を見ると、白い紙に包まれた木が十二本刺さっています。「これ何やろ?」。これは十二光仏の名を書いた斎串なのです。昔は道路を渡して架けていたのですが、両端に架ける大木がなくなったり交通の障害になったりし、てこのようにくるりと巻きあげて片方の木に結わえつけられるようになったようです。
勧請縄は東老蘇の外れにも架かっていました。昔は、どこのムラでもこうしたことが行われていたのでしょうが、こうしてしっかりと継承されているところは本当に少なくなりました。ふるさと学では、こんな民俗学的なことも探検しているのですよ。
Posted by 安土まち協 at 18:15│Comments(0)
│ころっけパパのひとりごと